
【トナカイ?】
山梨県郡内産業振興センター入口にありました。
可愛いですね。
雪景色の富士山がとってもきれいでした。
木馬の角が気に入りました。

【看板】
シンポジウムの看板です。
この地域産業振興センターには地場産のネクタイや工芸品など様々なものが並んでいて大変おもしろかったです。
もちろんお土産も購入することができますので富士吉田市へお越しの際にはぜひお寄り下さい。お勧めです。

【北都留森林組合のパネル展示】
今回は、ハイキングマップを中心に北都留森林組合の取組である林業体験教室などをご案内させて頂きました。
資料には北都留森林組合パンフと学校林活動(上野原小学校)を配布させて頂きました。
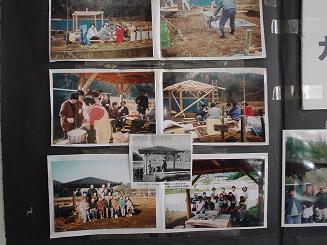
【カーカネットの会】
富士吉田市で活躍されている団体で美しい自然を活かした公園づくりをされています。この写真は東屋をつくられているところです。
連絡先(0555−22−0296)
代表者:加々美清子氏

【NPO富士に学ぶ会】
富士山周辺の自然環境の保全活動、森づくり・まちづくり活動を通じて指導者育成・青少年の健全育成などを目的に活動されています。
HPはこちら
http://www11.plala.or.jp/fjimanabu

【財団法人かながわ海岸美化財団】
神奈川県内全長150kmの自然海岸の清掃を実施するとともに、美化啓発活動、美化団体の支援、調査研究を行うことにより、海岸美化を図っている。
HPはこちら
http://www.bikazaidan.or.jp

【NPOあさひファーム】
これはBDF製造機です。
EM菌による堆肥の有効活用や乗馬公園の運営などによる福祉活動など幅広く活動されていらっしゃいます。

【大月森つくり会】
間伐材をつかった時計、ピクチャースタンド、画鋲などおもしろいものをたくさん展示されていました。
毎月第4日曜日に笹子の森で森づくり活動を展開されています。

【シンポジウム開催】
富士吉田市長萱沼俊夫氏の挨拶で始まりました。基調講演の講師、駄田井正氏の筑後川でのお話も大変参考になりました。
流域交流の大切さと実践されている話は大変参考になりました。

【パネルディスカッション】
流域の循環を考える−水は天下のまわりもの−と題して討論が展開されました。
ゴミの問題、意識の問題、経済の問題などたくさんの課題がありました。
いずれにしても一人一人の気持ちが大切であり、これから市民、行政、事業体、それから観光客も含めてかかわるすべての人々が一緒に問題解決していくことが必要であることを改めて実感しました。